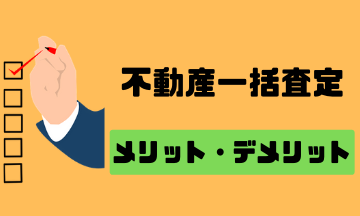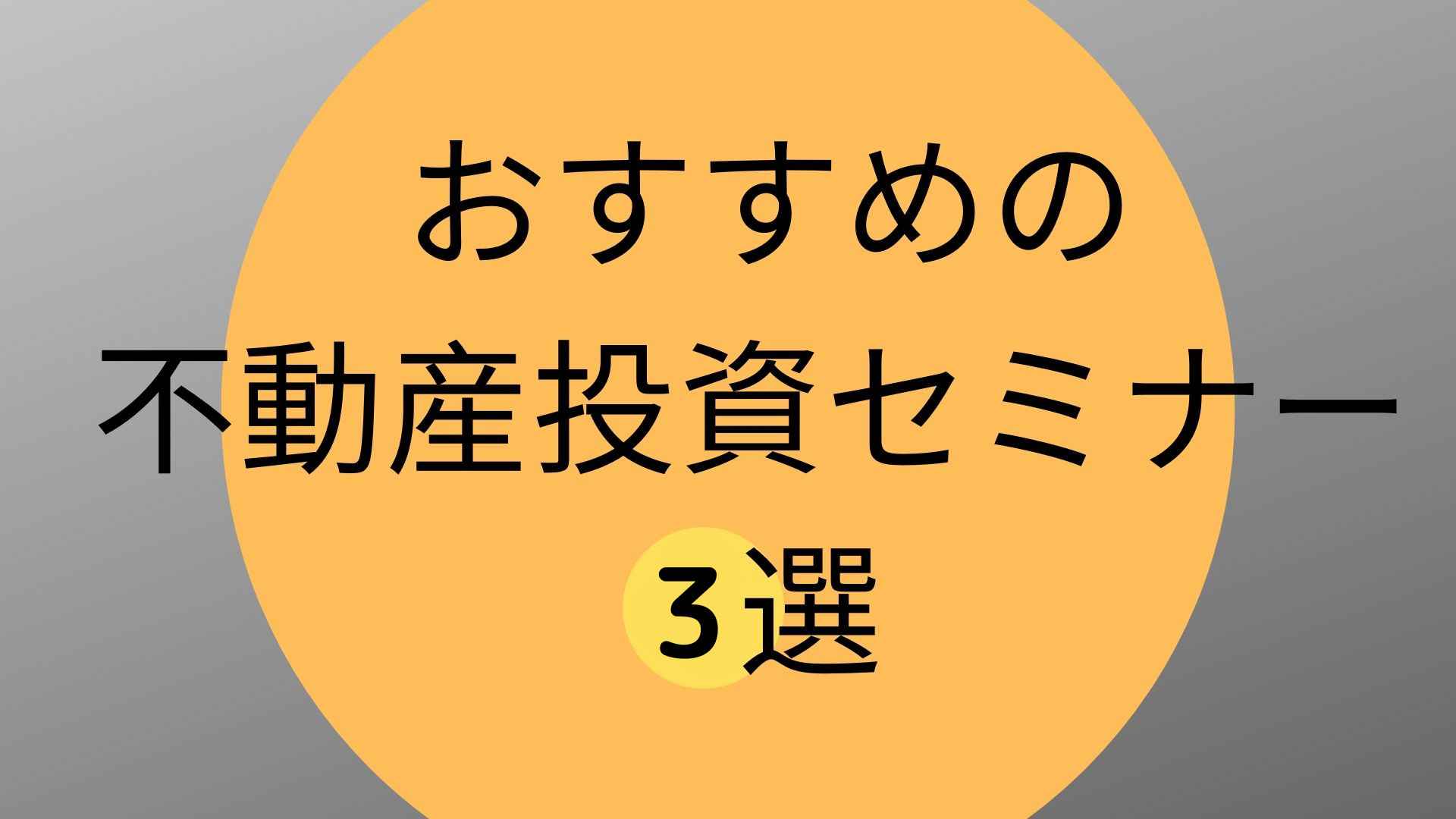固定資産税課税標準額と固定資産税評価額との違い


土地や家屋を購入すると5月に市町村から固定資産税の納税通知書が届きます。
毎年1月1日時点での土地や家屋の所有者に支払い義務があるのですが、登記簿に所有者として登録している人がその対象となります。
固定資産税は市町村の税収入の半分以上を占め市町村の運営や公的な施設の設置や管理、福祉、消防、水道などの維持や整備を進めるうえで重要な役割をしています。
納税額は市町村が定めた土地の価格をもとに算出された額に1.4%の税率をかけて求められます。
土地の価格は3年に1度の基準年度に見直されます。
土地には用途により商業地区、住宅地区、工業地区に分類され、さらに街路の状況や公共施設などが近くにあるかどうか、家屋の密集度などによる状況類似地域に区分されます。
そして状況類似地域の中で標準となる主要な道路・路線を選び、その路線に接する土地の中で位置や形状などが標準的なものを標準地として選び出します。
毎年1月1日にその標準地1㎡当たりの適正な時価を総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって決まり、国土交通省が3月か4月ごろ公表するのですが、その時価を「路線価」といいます。
この路線価をもとに不動産売買時の土地の価格相場や固定資産税、または相続税などが算出されていくのです。
固定資産税の対象となる課税標準額は路線価に基づいて算出されます。
路線価は3年に1度の見直しが行われ、各市町村のホームページや税務署でも公表しています。
路線価をもとにして土地の形や傾斜の有無、高い建物が建てられないなどの規制の有無、交通の便、生活の利便性などを加味しそれぞれの土地1㎡当たりの価格が算出され、その価格を土地の路線価ということになります。
住宅用地に関しては特例があり、200㎡までの住宅用の土地の6分の1に、200㎡以上の場合でもそれを超える部分については3分の1にしたものを課税対象にするという決まりがあります。
たとえば1㎡当たりの路線価が20万円で120㎡の住宅用地なら、20万円に20平方メートルをかけた額400万円が課税対象になるということで、その400万円を課税標準額といいます。
家屋の場合は同じ土地に再度新築の家屋を建てるならいくらかかるかという「再建築価格」に経年劣化を加味して算出するのですが、最建築価格は家屋の材質によって異なり、それは国税庁が「標準的な建築価格表」として公表しているのでそれを参考にし、経年劣化の係数をかけて算出します。
その額が家屋の課税標準額ということになります。
ちなみに経年劣化の係数は最低で0.2となっていて0になることはありません。
この課税標準額に1.4を乗じた額が固定資産税として算出されます。
つまり固定資産税を算出するにあたって課税氷筍額が必要になるのです。
固定資産課税標準額は毎年1月1日に決定する標準地の路線価をもとに、各土地について評価された額のことですが、住宅用地に関しては特例に従って算出された額ということになります。
では固定資産評価額というのは何のことでしょうか。
それは標準地の適正な時価、つまり路線価に70%を乗じたものです。
土地の評価額は現地の用途によって評価されたもので宅地の場合は公示地価の70%となっているのです。
マンションなどの場合は面積に応じて計算され、日当たりなどの状況は無関係に計算されます。
家屋の場合の評価額は家屋を新築した場合に係る費用を基準として評価されます。
評価額を用いるのは負担水準を求めるときです。
課税標準額が評価額に対してどの程度となっているのかを数値で表したもので、例えば負担水準によって住宅用地の特例のような負担調整措置が行われます。
例えば1年で地価が2倍になるような土地がある場合、固定資産税も2倍になってしまいます。
その土地を売却するならば土地の価格が2倍になると喜ばしいことですが、売る予定がなく所有をし続けるのに固定資産税が2倍にもなったら大きな負担となってしまいます。
そんな時、固定資産税が急激に2倍になるのではなく緩やかに上昇して何年もかけて2倍になるように調整してもらうことができます。
しかしその調整をするには本則課税標準額と負担水準がポイントとなります。
負担水準は前年度の課税標準額を本年度の本則課税標準額で割って100%を乗じたもので、前年度に対して今年度はどれくらい課税標準額に差が出たのかを意味し、今年度が高くなっていれば100%未満になり今年度が下がっていれば100%を下回ります。
負担水準が小さければ今年度は大幅に高くなり、大きければ大幅に低くなるということになります。
本則とは本来のという意味で負担調整をする前の課税標準額ということです。
住宅用地の場合など特例がある場合はその特例を適用した後の額ということになります。

固定資産税の税額を求める場合には、固定資産評価額から課税標準額を計算し、さらに課税標準額に一定の税率を乗じて税額を計算する方法が採られます。
そのため課税標準額は実質的に税額そのものの大きさに関わってくるとともに、前段となる固定資産の評価額そのものがわからなければ、計算の仕方もないということになります。
このような関係性を踏まえた上で、固定資産税の課税標準を考えることが重要です。
固定資産税とはいってもその対象としては土地・家屋・償却資産があり、家屋や償却資産に関しては、原則的には評価額そのものが課税標準額となるのに対して、土地は種類に分けて検討する必要があります。
土地や家屋の固定資産評価額の算定は、3年に一度やってくる基準年度ごとに行われています。
逆にいえばそれ以外の年度に関しては、原則的には前年度からの据え置きで固定資産評価額が決まっていることになります。
そのため課税標準もこの評価額に連動していると考えてよいといえます。
これは原則論ですので、土地については必要に応じて下落分の修正などが行われる場合があります。
また算出された固定資産評価額が前年度の評価額を超える場合には、その金額を引き上げることなしに前年度の評価額に据え置かれます。
土地のなかでも農業用や道路の敷地などとして用いられているものではなく、宅地に限っていえば、固定資産税の課税標準の計算上は、大きくは3つの種類に分類されています。
その分類とは、小規模住宅用地・一般住宅用地・非住宅用地です。
これらのいずれの種類に該当しているかで、課税標準の決まり方は大きく異なってくることになります。
いっぽうで小規模住宅用地以下のどの種類にもあたらないような土地に関しては、課税標準額と固定資産評価額は同額になっています。
これは家屋や償却資産の場合と取り扱いとしては同じと考えてもよいといえるでしょう。
土地の課税標準については、総務大臣が定めた固定資産評価基準の規定にもとづいて、いくつかのプロセスを追って算定されることになっています。
まずは不動産鑑定価格や地価公示などの結果をもとにして、地域と地目ごとに、土地の平米あたりの価格を求めます。
これは標準値単価などとよばれていますが、もしも市街地に該当する場合には、道路ごとに付けられた路線価という形式になります。
その上で平米あたりの価格にそれぞれの土地の地積を乗じたものが評価額となります。
宅地やこれに準ずる雑種地については、土地の形状や奥行などに応じた補正が行われます。
評価額と課税標準がイコールではない場合、前出の種類に応じてさらに計算が必要です。
宅地のなかでも小規模住宅用地とは、住宅一戸あたり200平米までの部分のことを指しています。
この場合の課税標準額は、固定資産評価額の6分の1の額です。
一般住宅用地とは、住宅の床面積の10倍までの部分から小規模住宅用地の面積を引いた部分にあたります。
この一般住宅用地の課税標準額は、固定資産評価額の3分の1の額です。
非住宅用地とは、これまでの小規模住宅用地および一般住宅用地以外の宅地のことであり、課税標準額は固定資産評価額の7割の額です。
ほかに宅地に準ずる雑種地の課税標準額についても、非住宅用地と同様に固定資産評価額の7割の額になります。
算定された課税標準額が前年度を大きく上回る場合は負担調整措置を講じます。
家屋の課税標準を計算する場合についても、総務大臣の定める固定資産評価基準にもとづきます。
まずは再建築価格といって、その建物を再び新築した場合にいくらの費用がかかるのかを算出します。
算定された再建築価格から、新築時からどれほど年数が経過したのかに応じた減価率を乗じて、その時点での評価額を算出します。
基本的にはこの評価額がイコール課税標準となります。
再建築価格を算定する上では、実際に市町村の職員が現場を訪れて調査をし、建物の構造や柱の本数などの要素を点数に置き換えて、その点数から逆算して建築費を見積もる方法が採られます。
そのため新築からしばらくすると市町村から調査の通知があります。
同じマイホームとはいっても土地や建物が明確に分かれている一戸建て住宅ではなく、分譲マンションやメゾネットなどの一室を所有し、そこにマイホームとして住む場合もあります。
この場合の課税標準の計算ですが、基本としては一戸建てのように土地と家屋に分けて計算しますが、一部気を付けたい部分がみられます。
たとえば土地に関しては敷地をそれぞれの居室の住民、いわゆる区分所有者で共有していますので、個々の住民に対しては共有持分に応じて分割課税がなされます。
家屋についても区分所有している居室の専有面積の部分を取り出して考えるのが基本ですが、そのほかにもエレベーターやベランダ、廊下などの共有部分も課税対象です。

課税標準額は、固定資産税と都市計画税を合わせた金額です。
これらは、土地の評価額によって定められ、固定資産税は地方税法の第350条より評価額の1.4パーセント、都市計画税は同じく地方税法の第702条の4より評価額の0.3パーセントと定められています。
つまり、合わせて評価額の1.7パーセントを税金として納めなくてはならないのですが、一定条件を満たした土地であれば、特例が適用されて課税標準額が安くなるのです。
この場合の住宅用地とは、居住のための家屋が建てられた土地のことを指します。
さらに、住宅用地は住宅1戸に就き200平方メートルの場合は小規模住宅用地、200平方メートルよりも広い場合は一般住宅用地に分類されます。
この分類は、特例率に関わってきます。
小規模住宅用地の場合、固定資産税は特例によって評価額の6分の1、都市計画税は評価額の3分の1となります。
一方、一般住宅用地の場合、固定資産税は評価額の3分の1、都市計画税は評価額の3分の2となります。
つまり、小規模住宅用地の方が、減額されやすいということです。
ただし、この特例は、住宅用地が完全に住宅として利用されている専用住宅の場合であり、住宅以外の目的で使用されている場合は、以下のように併用住宅として扱われます。
住宅用地であっても、店舗や更地などの住宅に使われていない土地がある場合は併用住宅と見なされ、その比率に応じて特例に対する計算式が変わってきます。
住宅用地の2分の1以上が住宅として利用されていれば、専用住宅と同じ扱いとなりますが、4分の1よりも多く、2分の1よりも少ない場合は、専用住宅の場合の50パーセントしか認められません。
さらに、住宅の占める割合が4分の1よりも少ない場合は、特例を利用することができなくなります。
また、地上5階以上の耐火建築物が併用住宅となっている場合は、4分の3以上が住宅であれば専用住宅と同様の扱いとなり、4分の3未満2分の1であれば75パーセント、2分の1未満4分の1以上であれば50パーセント、4分の1未満の場合は、特例を受けられない状態となります。
市街区内の農地の場合も、特例が認められます。
この場合は、固定資産税が評価額の3分の1、都市計画税が評価額の3分の2となり、一般住宅用地の特例と同様になります。
ただし、農地として利用されていることが前提となるうえ、特例が認められても、一般的な農地よりも固定資産税は高くなるため、注意が必要となります。
新築住宅の場合、居住部分のうち、120平方メートルまでの固定資産税が半額となる特例を受けられることがあります。
ただし、一般住宅の場合は3年、3階建て以上で耐火、あるいは準耐火建築物と認定された場合でも5年の期限があります。
ただし、後述する長期優良住宅の場合は、それぞれ2年が追加されます。
なお、これについては、都市計画税は適用外となります。
2009年に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されたことにより、長期優良住宅の認定という制度が始まりました。
これは、住みやすさやメンテナンス性、耐震耐火性やバリアフリー性など、各種のチェック項目が認定されれば、固定資産税の他にも、様々な特典が受けられるというものです。
固定資産税に限って言えば、上述の通り、新築住宅で固定資産税が半額となる年数が2年増えます。
1981年よりも前に建築された住宅を取り壊し、新築した場合は、3年間固定資産税が全額免除されます。
一方、建て替えの場合でも、1年の間、居住部分120平方メートル分の固定資産税が免除となります。
また、省エネ改修工事の場合は居住部分120平方メートル分の固定資産税が翌年だけ3分の1となり、バリアフリー化の場合は、居住部分100平方メートル分の固定資産税が、同じく3分の1となります。
ただし、いずれも3か月前に申告する必要があるうえ、省エネ改修工事とバリアフリー化は、一度しか利用することができません。
さらに、いずれの場合でも、地方自治体ごとに細かい条件の違いなどがあるため、これらの特例を利用したい場合は、事前に条件を確認しておくことが推奨されます。
例え住宅用地に住宅が建っていたとしても、空き家の場合は特例が認められないこともあります。
これは、空き家の中でも、倒壊の危険性や衛生面、景観面の問題があり、市町村が所有者に対して警告を発する特定空家に指定されている場合です。
特定空家は2015年の地方税法改正により、第349条の3の2として初めて設けられたため、長い間空き家を放置していた場合は、特に注意しなければなりません。

固定資産税の税額を決定する際には一般的に路線価と呼ばれる不動産の評価基準額をもとに決定する事になりますが、路線価は3年ごとの調査により決定されるため、3年間の間に不動産の路線価が高騰することが有る為これに基づいて固定資産税の税額を決定すると急激にその税額が高騰する事になってしまい、様々な問題を生じることになりかねません。
そのため、路線価が急激な高騰や下落をした場合にはその課税額を決定するために、固定資産税の課税標準額に一定の税率を乗じて固定資産税額を決定する事が行われます。
これを負担軽減率と言い、急激に土地の価格が変動する可能性の高い地域などではよく適用されています。
固定資産税額の決め方は、基本的には不動産の路線価に一定の係数を乗じて決定する事になります。
その為、路線価が高騰した場合にはこれに添って固定資産税額も上昇します。
一般的に路線価は国土交通省が決定する全国の地区ごとの不動産価格を受けて各都道府県がその地域の特異性を加味し決定する事になりますが、場合によっては同じ地域でも大きく路線価が異なってしまうこともあり、その想定には様々な要素が加味されることも多いのです。
不動産の路線価は国土交通省が決定する場合には都道府県や地方単位で決定する物となるため、周辺で格差が生まれることは少ないのですがこれを各都道府県が精査した場合には地域の特性により格差が発生することも少なくありません。
これはその地域の将来の発展性やこれまでの人口の推移などを都道府県が加味するためで、周辺と固定資産税の税額が異なると言って誤りと判断することはできない事になります。
固定資産税は地方税で有る為、その税率や税額は地域によって異なります。
これより金額の変動やその範囲も地域によって異なるため、負担軽減率が適用されるケースも地域により異なることになります。
その点を認識しておかないと税額に関してトラブルを生むことになってしまうため、十分な注意が必要です。
負担軽減率は路線価が急激に高騰した場合や下落した場合に適用されるものとなっていますが、実際にはその基準となるのが課税対象額となる不動産価格の変動の割合に依存します。
課税対象額は土地の使用目的やその他の理由により異なるため、同じ広さの土地であっても利用目的により負担軽減率が適用されたり、されなかったりといった事が有る為注意が必要となります。
土地の固定資産税は利用目的によって異なります。
一般的に住宅地として使用している場合には課税対象額がその他の目的に使用している場合の1/6となるため、税額もこれに準じたものとなることになりますが、その土地自身の路線価が変動した場合には課税対象額の変動の金額により負担軽減率の適用が行われるかどうかが判断されることになるのです。
従って、住宅地以外での利用がされている土地については負担軽減率が適用されるが、住宅地として利用されている土地については適用されないケースも有る為注意が必要となります。
急激な路線価の変動により固定資産税が変動することは都道府県の税収に大きな影響を及ぼしてしまうことになるという背景もあります。
その為、急激な変化が予測される場合には路線価の変動に関わらず固定資産税の据え置きが行われることも少なく有りません。
また、急激な税額の変化が予測されその変化が前年度の税額の70%以下となる場合にはこの税額の変動を前年度の70%までとすることが法律で定められています。
その為、路線価の下落によりその評価額が半分以下となってしまうような場合でも、固定資産税の減額は前年度の70%の金額に抑えられてしまうことになるので注意が必要です。
このように負担軽減率の影響は税額が低くなる場合にも適用されるので注意が必要となるのです。
負担軽減率は急激な税額の変化を抑えるために利用されるものですが、この適用は必ずしもおこなわれる物ではないことを知っておくことが必要です。
その適用は各都道府県の判断において行われており、必要に応じて利用されるものとなっているためです。
さらに建て替えなどで新築の住宅を建築した場合にはその住宅の評価額に応じて路線価が高騰し税額が高額となる可能性も少なくありません。
この場合住宅の税額と合わせると大きな変動が発生しますが、この場合の住宅の税額には軽減措置は発生しないため、税額が急激に高騰することも有る為注意が必要です。
住宅については負担軽減率の適用はありませんが新築住宅に関する減額措置やバリアフリー住宅に対する減額措置などが有る為、これらを有効に活用することが必要となります。
不動産売却に関する新着コラム
-
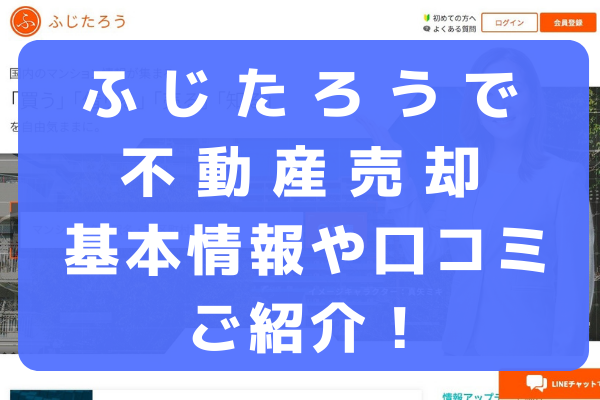 ふじたろうで不動産売却。基本情報からメリットデメリットま...
ふじたろうで不動産売却。基本情報からメリットデメリットま...今回の記事は、ふじたろうの不動産売却について徹底解説していきます。 ふじたろうの不動産売却の評判や口コミ、特徴まで詳細に説明していくので、不動産売却にご興味が...
-
 これを知らないとアパート経営であなたは失敗します。失敗談...
これを知らないとアパート経営であなたは失敗します。失敗談...アパート経営を考えていく上でリスク管理を避けて通ることはできません。この記事ではアパート経営のリスク・失敗談とその回避方法を紹介しています。
-
 定期借地権マンションは買ってはいけない?メリットとデメリ...
定期借地権マンションは買ってはいけない?メリットとデメリ...不動産投資をはじめとした土地の購入でたまに見かけることのある「定期借地権付き」。相場よりなぜ値段が安いのか?どんなデメリットがあるの?を徹底解説!
-
 株式会社エスティアの不動産投資は実際どう?口コミ・評判・...
株式会社エスティアの不動産投資は実際どう?口コミ・評判・...今回は、首都圏に展開する株式会社エスティアについてご紹介します。特徴・不動産投資・評判・口コミ・強み・申し込みまでの流れを詳しく記載しています。ぜひ参考にしてみ...
不動産売却に関する人気のコラム
-
 不動産売却6つの注意点!知らないと〇〇千万損する?[徹底...
不動産売却6つの注意点!知らないと〇〇千万損する?[徹底...不動産売却にはその流れの中でいくつか気を付けるべき注意点や成功するためのコツがあります。 不動産売却の流れに沿って一つ一つ紹介していきます!
-
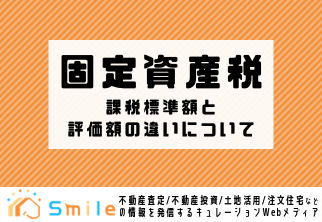 固定資産税課税標準額と固定資産税評価額との違い
固定資産税課税標準額と固定資産税評価額との違い固定資産税課税標準額をご存知ですか? 実は、固定資産税課税標準額を知っていることで得になることもあるのです
-
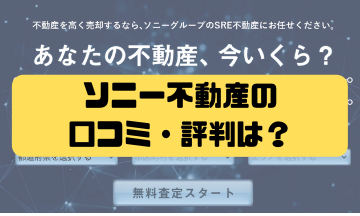 [最新版]ソニー不動産の口コミ・評判・業績は?失敗談も紹...
[最新版]ソニー不動産の口コミ・評判・業績は?失敗談も紹...ソニー不動産の特徴的な売買システム「エージェント制」。一見顧客目線のいいサービスのように思えるが、実際は赤字が続いていたそうです。では、ソニー不動産での不動産売...
-
 固定資産税とは?土地・家屋別の計算方法を解説
固定資産税とは?土地・家屋別の計算方法を解説固定資産税の計算方法の仕組みって難しいですよね。 実際に、土地や家屋別によって計算方法は変わってきます。 是非、参考にしてみてください!