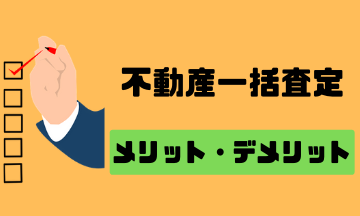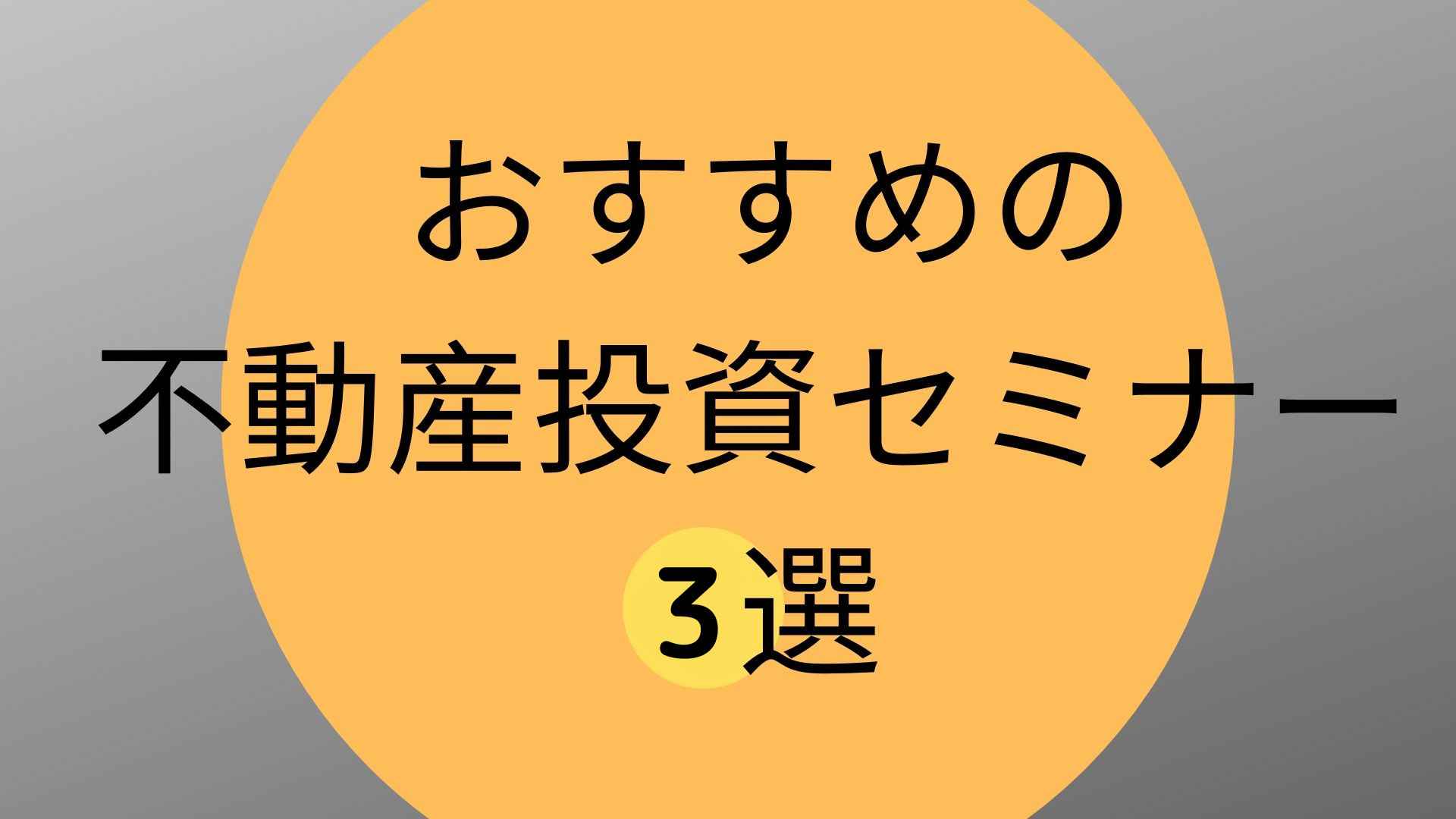登録免許税って?減税措置や計算方法を徹底解説!

登録免許税という言葉を聞いても何となくぴんと来ないという方も多いです。
普段はあまり接することがない税金の一つということができます。
どういったときに支払うものなのかわからないけれど耳にした、目にしたという方もいるかもしれません。
特に不動産を購入するときに初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。
登録免許税がどういった税金なのかについてチェックしてみましょう。
多くの方が初めて登録免許税を意識するのが、不動産を購入するときではないでしょうか。
家や土地などの購入費用に加えて、税金が必要になるということに驚いた方も多いでしょう。
様々な税金がありますが、購入時にかかる大きなものとして登録免許税があるのです。
不動産の売買をする際には登記をすることになります。
特に土地を購入した場合はきちんと手続きをしておかないと、権利を失ってしまうこともあるのです。
きちんと税金を納めて申請することで、権利を守ることができます。
このような役割のあるものとしてこの税金をとらえておきたいものです。
登記をするときは何も不動産を購入した場合だけではありません。
相続した場合なども名義をかえる必要があり、その時に税金がかかることになります。
義務ではないのですが、その都度行っておかないと所有者が不明になり、売却する際や公共の必要性が生じた時などに関係者を探すことが難しくなっていきます。
このような形で社会問題となっているケースも多いものです。
また、抵当権など不動産に別の権利を付けた場合にも登記が必要になります。
借りた場合なども条件によっては登記をすべきことがあるのです。
不動産について何らかの権利を取得した時や変更があった時に登記の必要性と登録免許税がかかるということを覚えておきましょう。
不動産に関する登録免許税についてかかわったことが初めてという方も多いでしょうが、それ以外の場面でも登録免許税は発生します。
例えば船舶や航空機などを登録する際にも不動産と同様な形で発生することになります。
それ以外でも、例えば免許の必要な仕事につく場合に、その免許を受けた時、登録するときなどに登録免許税が発生することがあるので、登録免許税は様々なところでかかわってくるものと意識しておくとよいです。
登記をするときに登録免許税がかかるということですが、なぜお金を納めて登記をしなければならないのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
土地の価格が高くなれば、それだけ登録免許税の負担も大きくなります。
できれば避けたいと思う方もいるかもしれません。
不動産の場合、今のところ登記をすることは義務ではありませんから、負担の大きさを考えるとわざわざ登記をしなくてもいいのではないかと思う方もいるでしょう。
しかし、きちんと登記をしておかないと困ることもたくさんあります。
なぜ高い税金を納めて登記しておくべきなのかを確認して、適切な手続きを取っていくようにしましょう。
基本的に買った土地は自分のものになるのが当たり前のことではありますが、同じ土地を売主が他の人にも同時に売っていたらどうなるでしょうか。
どちらも買ったという点では同じ条件ですから、何かほかに持ち主を決めるためのポイントが必要になります。
それが登記ということになるのです。
なくしたくない物に名前を書くように、購入した土地に登記をしておくのです。
そうすることで他の人もその土地に誰の権利があるかわかりますし、万が一二重に売られていたとしても自分のものだということを主張することができることになります。
高い登録免許税を納める必要がある第一のポイントはこうしたところにあるのです。
他にも、借りたことを示したい場合、抵当権を付けたことを示したい場合などにも同様に権利を守るために適切な手続きをする必要があります。
売買をして権利が移動した場合は、二重に売られるなどという形で権利を失う恐れがありますが、所有者が亡くなったことで相続した場合などはそういった恐れがないので登記をする必要がないと考える方もいます。
実際数代にわたって登記されていない土地なども多くあります。
売買の場合に比べると登記しないままになりがちですが、そのままにしておくと後で大きな問題が生じることがあるのです。
売却しようと思ったときに、売主にあたる相続人が全員で手続きをする必要が生じますが、数代にわたって相続登記がされていないままになっていると、関係者の数が膨大になってしまうことがあります。
中には音信不通になっているという方もいるでしょう。
そうなると登記ができませんから売ることができなくなってしまうのです。
こうしたことを防ぐために、所有者をはっきり示しておくことができるように手続きをしておくことが必要になります。
登記申請の際に登録免許税を納めることになりますが、多くの場合司法書士などの専門家が代理をすることになるので実際に自分でおさめたという意識がない方も多いです。
大きな金額が動くものですから、その内訳についてはきちんと確認しておきましょう。
登記の種類によって登録免許税の計算方法は異なってきます。
基本的には一定割合を不動産の課税価格にかけて計算することになります。
所有権が移る場合にはたいていこのケースです。
条件によって軽減されるケースもありますので、専門家に相談してみるのがおすすめです。
抵当権などを設定するときには債権額などに一定割合をかけて計算していくことがあります。
住所の変更や、抵当権の変更をする場合などは定額になっていて、不動産の個数によって増えていくことになります。
基本的には不動産の権利に関することには登録免許税がかかることになりますが、中には非課税になるものがあるのです。
例えば不動産の状態について示す表示の登記は非課税となります。
他にも国や地方自治体などが不動産を購入した場合などには非課税になります。
こうした例外もありますが、基本的には登録免許税は納めるものととらえて準備をしておきたいものです。
登録免許税は、不動産にかかわる税金の一つ、登記時に必ず納める必要がある税金です。
しかしながら登記と言っても、不動産取得時もあれば、会社設立時もありますし、登録免許税の範囲には、
- 特許
- 免許
- 許可
- 認可指定
- 技能証明 など
上記したもののような様々なものが課税範囲になります。
この内、不動産取得においては、不動産登記を受ける者に対し、登録申請を行う際に国が課税する税金などの特徴を持ちます。
不動産以外にも多数の登記などが対象になるなどの理由から、登録免許税の名称が付いているわけです。
指定や技能証明など様々なものが課税範囲になります。
この内、不動産取得においては、不動産登記を受ける者に対し、登録申請を行う際に国が課税する税金などの特徴を持ちます。
不動産以外にも多数の登記などが対象になるなどの理由から、登録免許税の名称が付いているわけです。
登録免許税は、誰が税金を納めなければならないのでしょうか。
これは登記を受ける人が納税義務者であり、複数の者が登記を受ける場合は、連帯納付義務を負うことになります。
不動産売買の時には買い主側(権利者)と売り主(義務者)が連帯する形で納付義務を負うことになるのが特徴です。
土地を他の人が購入する時、売り主から買い主に所有権移転登記と呼ぶ名義変更をするケースが多いかと思われますが、この場合は、売り主と買い主が連帯する形で国に対し、登録免許税を納める義務が発生します。
現代においては、登記により利益を得るものである買い主側が全額負担を行うことが一般的で、売り主側が負担することはほとんどありません。
ちなみに、売り主側は不動産登記の抹消を司法書士に依頼することになりますが、この時の報酬については売り主側は支払いが生じるケースが多いため事前に費用を確認しておくと安心です。
この税金は、双方の合意があれば折半で費用負担することも出来ますが、支払額に上乗せが行われる可能性もあるなどからも、買い主側が負担するのが一般的です。
不動産を購入した時の登録免許税の納付ですが、これは登記を受ける時までに、土地建物の所在地を管轄している登記所の所在地に対して、現金で納める必要があります。
但し、登録免許税は、国税の収納機関に現金で納付を行い領収書を受け取り、領収書を申請書類に貼り付けて期間内に提出して納付する方法もあります。
こうして考えると、結構面倒だし書類の作成も自分でやらなければならないなど、ハードルがとても高くて難しいなどのイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。
基本的にはこれらはすべて司法書士が代理人をつとめてくれるなど、司法書士に費用の全額を支払う、登録免許税の納付を初め、登記申請書類の作成や提出などの手続きをお願いすることが出来ますので、買い主側が納付の仕方や手続きについて不安に感じる必要はありません。
登録免許税は必ずしも課税対象になるものではありません。
例えば、国や地方公共団体、公益法人などが自己のために受ける特定の登記については非課税です。
分筆や合筆を除いた表示登記、委託者から受託者への信託財産を移す時の所有権などの移転登記、信託契約時から引き継ぎ、委託者だけが受託者である場合など、これらはいずれも非課税の取り扱いになります。
一般的な不動産売買においては課税対象です。
土地を購入して注文住宅を建築し、マイホームを作る場合、中古マンションや中古一戸建てを購入する時、新築分譲住宅や新築マンションを購入する時は課税対象になるなど、マイホーム購入は登録免許税を納める必要があることを把握しておきましょう。
マンションや一戸建て、土地を購入すると消費税や登録免許税などの税金を納める必要があります。
消費税については、仲介業者からの紹介で中古一戸建てやマンションを購入した時、仲介手数料を支払う必要があるわけです。
この手数料は消費税が課税されることになり、現金で納める形が一般的です。
登録免許税も購入側が負担する税金ですから、それぞれの計算方法を把握しておくことをお勧めします。
登録免許税の計算方法は、課税標準×税率=税額です。
課税標準は、不動産価格、債権金額不動産の個数などで、不動産価格は原則登記申請時の固定資産税評価額です。
尚、課税標準の価格は申請日に応じて変わるのが特徴です。
登記申請日が1月1日から3月31日まで間に申請を行った時は、前の年の12月31日の登録価格です。
申請日が4月1日から12月31日までの場合は、当年1月1日時点の登録価格になるなど、3月31日まで、4月1日以降では価格が変わることになります。
これには条件があり、固定資産課税台帳登録価格がある場合で、価格がない場合は登記期間が認定した価格になります。
固定資産課税台帳登録価格は、登記申請を行っている場合の値段であり、簡単に言えば中古物件がこれに該当します。
固定資産課税台帳登録価格がないケースは、新築建物の所有権保存登記時に、登記申請時に登録価格がないケースです。
土地については不動産と言う形で売買取引が行われることになるなどからも、固定資産課税台帳登録価格は3月31日と4月1日では納める金額が変わることになります。
登録免許税の計算式に出て来る、課税標準は不動産価格と債権金額、個数などになりますが、債権金額は抵当権設定登記の債権額、住宅ローンを利用した時などに発生する金額です。
不動産の個数は、
- 土地の分筆
- 更生
- 変更
- 抹消
など、不動産一つずつに1,000円がかかることを意味しています。
登録免許税は買い主側だけが支払うケースが多いのですが、土地や建物には一定の条件を満たしている場合、特例を受けることが出来ます。
土地の売買では、平成31年3月31日までの間に行う場合は、1,000分の15の軽減税率の特例を受けることが可能です。
但し、これは売買の場合で、相続や法人合併などは特例がありません。
建物の場合は、住宅の種類が自己居住用住宅であり、床面積が50平米以上、築20年以内もしくは地震に対する安全性に係る基準に適合、その他の条件を満たしている場合は特例が適用されるなどのメリットがあります。
マンションや一戸建て、土地などの不動産を購入した際には仲介手数料や住宅ローン事務手数料などの費用に課税される消費税、不動産登記時に課税が行われる登録免許税などの税金を納める必要があります。
仲介手数料や住宅ローン事務手数料などの税金は、仲介手数料であれば仲介業者でもある不動産会社からの請求時に上乗せされます。
住宅ローン事務手数料もローン会社や金融機関からの請求で上乗せされるなど、税務署などへの申告などを行う必要がありません。
登録免許税においては税金を納める形で行いますが、不動産登記は自らが行うことも可能ですが、一般的には司法書士に一任する、費用全額を司法書士に渡すことで登記申請手続きや課税対象となるお金の支払いなどを一括で行って貰うなど、自分がやらなければならないわけではないので安心です。
登録免許税は、不動産登記だけでなく、登記されているものを抹消する時にも課税対象となります。
登記申請は、購入側が行うもので、マイホームや土地などの所有権を得るために行うもので、抹消手続きは、この所有権を移転させるために行うものです。
通常、登記申請は購入側が行い、これに伴う税金は買い主が出す形になり、抹消に伴う税金は売り主側が出す形になるわけですが、最近は購入側が全額負担をするケースが多く、売却時に登録免許税を納めることは殆どありません。
不動産の売買契約を初め、相続などによる所有権の移転登記、所有権保存や抵抗権の設定登記などの申請は登録免許税法と呼ぶ法律で定められている税金を納める必要があります。
この税金のことを登録免許税と呼びますが、他と区別するために登記代などと呼ぶ人も多いのではないでしょうか。
ちなみに、登記代とも言える税金は課税標準に税率を掛け合わせた金額で求めることが出来ます。
課税標準は、登記に種類に応じて、不動産の価額に寄るケース、債権金額に寄るケース、不動産の個数に寄るケースの3種類が存在しています。
市区町村役場では固定資産課税台帳で管理を行っており、台帳に価格が掲載してある場合は、その金額が課税標準額になります。
市区町村役場で管理を行っている固定資産課税台帳の価格は、市区町村役場で発行している証明書内で、本年度価格や2018年度価格、評価額などと表記が行われているもので、固定資産税課税標準額とは異なるので注意が必要です。
固定資産課税台帳の価格がない時には、登記所が認定した価額、国が認めた金額になりますので、購入する不動産の所在地を管轄している登記所内で問い合わせを行うことで分かるようになっています。
但し、これについても、購入側が自ら調べるのではなく、司法書士に依頼することですべての業務を一任して貰えます。
土地の売買などの場合、4月1日より翌年の3月31日まででは1000分の15、翌年の4月1日からは1000分の20の税率になり、土地以外の不動産では1000分の20の税率で求めることになります。
個人が一定の条件を満たしている住宅家屋を購入した時、市区町村が発行を行う証明書の添付により、軽減措置が設けられています。
購入してから1年以内に所有権の移転登記を受けるものであること、要件に応じて1000分の1から1000分3までの税率に軽減されるなど、登録免許税の節約効果が期待出来るわけです。
一定の要件を満たすことで、課税額は軽減される仕組みになりますが、基本的な登記代の求め方を把握しておくことも大切です。
不動産売買においては所有権移転登記が必須事項としてあり、売り主の所有権を買い主の所有権に移転させるための手続きを行います。
この時、固定資産税評価額とそれぞれの税率を掛け合わせたものが登録免許税の税額であり、一般的には納税者は購入側になるケースが多いのです。
ここで求めた金額は、1,000未満の端数は切り捨てとなり、税額を計算した金額で1,000円未満の時には1,000円になることも覚えておきましょう。
所有権移転登記には不動産売買と相続、贈与などの種類があり、売買の場合には土地および建物に応じて税率が異なります。
土地の売買は、3月31日までは1000分の15、4月1日以降は1000分の2の税率になり、建物は時期に関係なく一律1000分の20になります。
尚、建物は1000分の3の軽減税率の措置が設けられており、通常納める金額よりも少ない、節税効果を期待出来るケースがあります。
中古住宅における移転登記に軽減特例が認められているのですが、中古住宅であればすべてではありません。
軽減の特例を受けることが出来る条件、これを把握しておけばマイホーム探しをする時にも役立ちますし、支払う金額も少なくなるなどのメリットにも繋がります。
軽減特例を受けることが出来るのは、中古住宅の建物に対する固定資産税評価額です。
但し、すべての中古住宅の建物が対象となるわけでなく、個人の自己居住用であること、住宅取得後に1年以内で登記を受けるものなどの必要要件があります。
他にも、登記簿面積の床面積が50平米であること、マンションなどの場合は耐火建築物であること、取得日以前に25年以内であるなどの要件も満たしている必要があるわけです。
木造などの耐火建築物以外の場合は、20年以内に新築されているなどは、1000分の3の軽減特例が適用されることになります。
要件を満たしていれば、軽減特例が適用されるわけですが、この特例を受けるためには住宅用家屋証明書と呼ばれている書類が必要です。
尚、取得日の年数が超えている場合、適用されないと諦める人も多いかと思われますが、このようなケースでも取得した住宅が新耐震基準に適合していることを証明出来れば適用範囲に含まれます。
耐震基準適合証明書を提供可能な時、依存住宅売買瑕疵保険に加入しているなど、登録免許税の軽減措置が適用されることになります。
登録免許税とは?、登録免許税法などの法律で定められている税金を意味しており、売買や相続などによる所有権の移転登記を初め、所有権保存登記や抵当権の設定登記などの申請時に課税が行われるものです。
この税金の計算方法は、固定資産税評価額×それぞれの税率で求めることが可能で、一定の要件を満たす中古マンションや中古一戸建てについては税額が1000分の3の軽減措置が適用されます。
軽減の適用を受ける時には、住宅用家屋証明書が必要になりますが、この証明書は市区町村長発行によるものです。
不動産売却に関する新着コラム
-
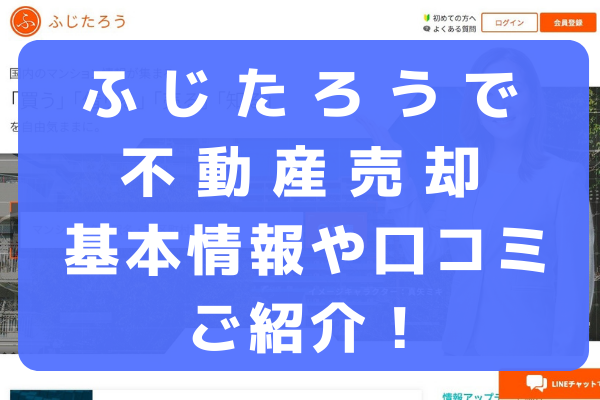 ふじたろうで不動産売却。基本情報からメリットデメリットま...
ふじたろうで不動産売却。基本情報からメリットデメリットま...今回の記事は、ふじたろうの不動産売却について徹底解説していきます。 ふじたろうの不動産売却の評判や口コミ、特徴まで詳細に説明していくので、不動産売却にご興味が...
-
 これを知らないとアパート経営であなたは失敗します。失敗談...
これを知らないとアパート経営であなたは失敗します。失敗談...アパート経営を考えていく上でリスク管理を避けて通ることはできません。この記事ではアパート経営のリスク・失敗談とその回避方法を紹介しています。
-
 定期借地権マンションは買ってはいけない?メリットとデメリ...
定期借地権マンションは買ってはいけない?メリットとデメリ...不動産投資をはじめとした土地の購入でたまに見かけることのある「定期借地権付き」。相場よりなぜ値段が安いのか?どんなデメリットがあるの?を徹底解説!
-
 株式会社エスティアの不動産投資は実際どう?口コミ・評判・...
株式会社エスティアの不動産投資は実際どう?口コミ・評判・...今回は、首都圏に展開する株式会社エスティアについてご紹介します。特徴・不動産投資・評判・口コミ・強み・申し込みまでの流れを詳しく記載しています。ぜひ参考にしてみ...
不動産売却に関する人気のコラム
-
 不動産売却6つの注意点!知らないと〇〇千万損する?[徹底...
不動産売却6つの注意点!知らないと〇〇千万損する?[徹底...不動産売却にはその流れの中でいくつか気を付けるべき注意点や成功するためのコツがあります。 不動産売却の流れに沿って一つ一つ紹介していきます!
-
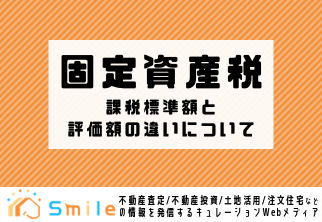 固定資産税課税標準額と固定資産税評価額との違い
固定資産税課税標準額と固定資産税評価額との違い固定資産税課税標準額をご存知ですか? 実は、固定資産税課税標準額を知っていることで得になることもあるのです
-
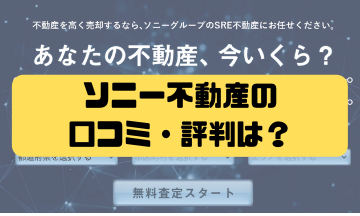 [最新版]ソニー不動産の口コミ・評判・業績は?失敗談も紹...
[最新版]ソニー不動産の口コミ・評判・業績は?失敗談も紹...ソニー不動産の特徴的な売買システム「エージェント制」。一見顧客目線のいいサービスのように思えるが、実際は赤字が続いていたそうです。では、ソニー不動産での不動産売...
-
 固定資産税とは?土地・家屋別の計算方法を解説
固定資産税とは?土地・家屋別の計算方法を解説固定資産税の計算方法の仕組みって難しいですよね。 実際に、土地や家屋別によって計算方法は変わってきます。 是非、参考にしてみてください!